| まとめ 保土ヶ谷付近の街道の変遷図 目次へ |
| ここで保土ヶ谷付近の古街道とその変遷をまとめておく。前著「桜ケ丘の歴史」で示した街道変遷図を、その後の研究成果を加えて大幅に改訂したものである。 「前期鎌倉道」と「権太坂がまだなかった頃の境木越え」ルートが付け加えられている。 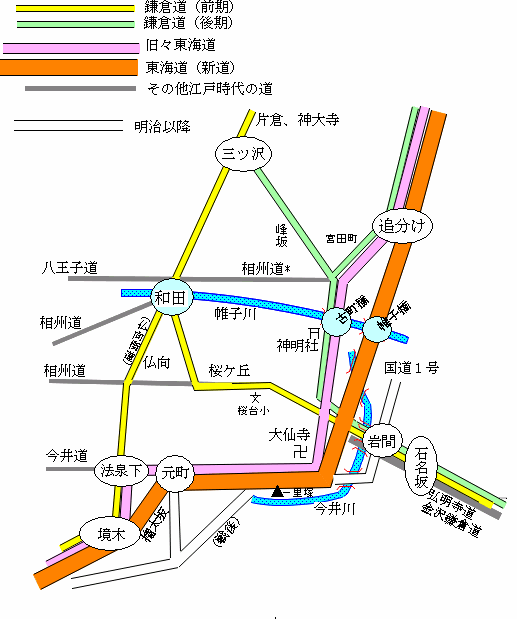 |
| まとめ 保土ヶ谷付近の街道の変遷図 目次へ |
| ここで保土ヶ谷付近の古街道とその変遷をまとめておく。前著「桜ケ丘の歴史」で示した街道変遷図を、その後の研究成果を加えて大幅に改訂したものである。 「前期鎌倉道」と「権太坂がまだなかった頃の境木越え」ルートが付け加えられている。 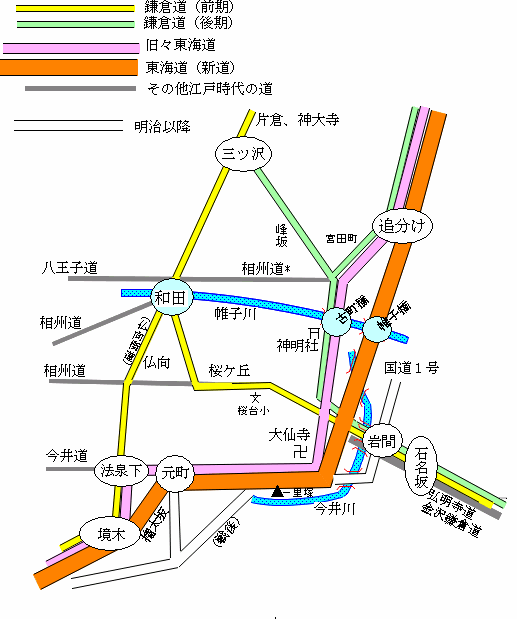 |
| 交通路の変遷 | ||
| (1)かまくらみち(鎌倉室町時代) 保土ヶ谷に至るまでの鎌倉道の経路: 品川-池上-矢口の渡し- 中略 -岸根公園-神大寺小学校- 神大寺/片倉町界-中丸小学校-三ツ沢下町-和田- 和田で帷子川を越えた鎌倉道は2つに別れる。 <鎌倉下の道> この当時、岩間村は鎌倉下の道/石名坂付近の宿場であり、保土ヶ谷(元町) は仏向街道/境木越えの宿場であった。 |
||
| (2)かまくらみち(戦国時代後半)
海面低下(海退)により、低湿帯が通れるようになり、川沿い海沿いの道が 開け始める。神奈川-浅間下-の海岸沿い鎌倉道が開ける。 ③-神奈川-浅間下-古町橋-ごてんば横町-石名坂- |
||
| (3)旧々東海道(慶長6年
) ②と③をつなげる形で東海道が制定される。桜ケ丘道は街道から完全に取り残され、桜ケ丘にあった神明社は東海道沿いの平地に移遷する。 ④-神奈川-浅間下-古町橋-神明社鳥居前-帷子町郵便局裏(ごてんば横町)-大仙寺下-法泉下-境木- 大仙寺-元町間の旧々東海道は今井川沿いにあった。この時代権太坂はまだ出来ておらず、旧保土ヶ谷町の中心部は法泉下付近にあった。 |
||
| (4
)東海道新道(慶安元年 ):街道が広い場所に平行移動する。 ⑤帷子、神戸、保土ヶ谷が新東海道沿いに集まり、保土ヶ谷宿が形成される。法泉下に一部残留(旧元町) ⑥旧岩間も少し遅れて、東海道沿いに移る。 |
||
| (5)権太坂の開削(万治2年
):元町-境木間が近道になった。 (旧元町)は東海道からはずれるため、権太坂下に移転(新元町)、4町1宿が完成する。 新道(新町)工事と権太坂開削工事は本来一体となった第1期工事、第2期工事であったと考えている。 |
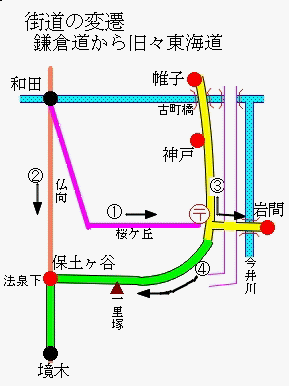 |
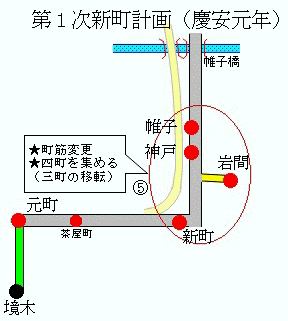 |
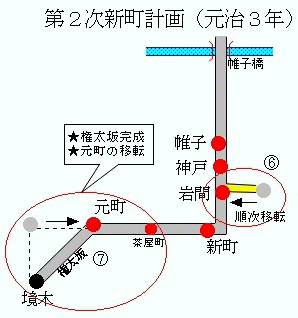 |
| 権太坂と旧保土ヶ谷付近について補足説明 旧保土ヶ谷の位置および権太坂開削以前の街道ルートについては、主として慶長14年検地帳に出て来る地名の研究から推定したもので別著で詳述するが、本図を眺めて頂くだけで次のようなことが明白であろう。 保土ヶ谷一里塚と品濃一里塚の間の距離が
一里に500m足りないことが保土ヶ谷区郷土史の指摘されており、その理由として「坂路や難所のある地点は気をきかして短縮していると思われる」と考察している。 |
||
権太坂がない時代の交通路は「法泉下-境木」であった。権太坂は近道として作られた。 |
||
| ★権太坂が作られたのは、東海道新道が出来てから更に11年も後のことであり、これまで見てきた保土ヶ谷地区の街道の歴史全体の中では非常に遅い時期である。 和田が帷子川の渡河点であった時代、上図から分かるように、境木からまっすぐ北上するのが最短距離であり、権太坂は必要がなかった。 渡河点が帷子川下流に移ったあと従来のコースでは直角三角形の2辺を通る遠廻りになるため、近道である権太坂が計画設計された。すなわち権太坂は渡河点の変化に対応して開かれたものなのである。 長い年月の間に生活の知恵として生まれた自然発生な道と較べて、権太坂のような人工的に地図の上で設計した道には、どこか無理なところがある。 |
||
| この看板では、「名前の由来」の問題としか取り上げられていないが、「万治2年開削」の情報の方が重要。 東海道が出来、さらに東海道新道や保土ヶ谷新町が出来上がったあとも、権太坂はまだなかったのである。 |
||
| 追記: 保土ヶ谷付近の交通路変遷の歴史の中で、「石名坂」の重要性を強調しておきたい。 旧鎌倉道の道筋は、前述のように時代により変化しており、また北向地蔵--弘明寺の間には3~4通りの複数ルートがある。しかし鎌倉道は一貫して石名坂を通っており、江戸時代に東海道が出来た後の弘明寺道、金沢鎌倉道もこの坂を通過した。石名坂は保土ヶ谷付近の交通路の中でもっとも長い歴史を持つ道なのである。 |
||
| 目次へ |