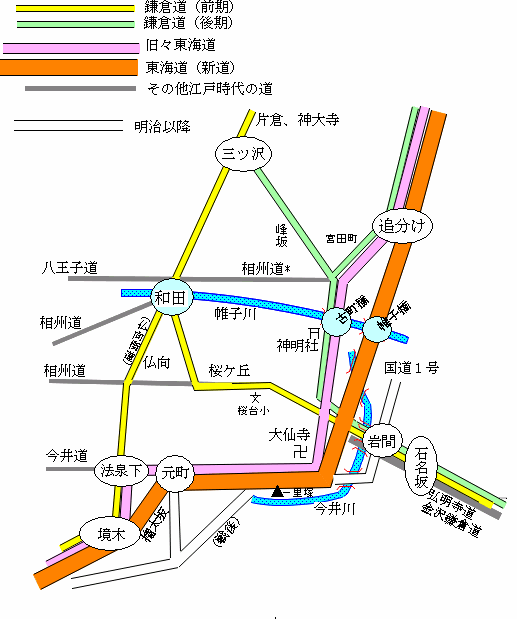| 桜ケ丘の歴史 2011改訂 大畠洋一 保土ヶ谷目次へ | |
| 目次 まえがき §1 古代の桜ケ丘 §2 鎌倉室町時代の桜ケ丘−鎌倉道(前期鎌倉道) 2-2 もう一つの鎌倉道−保土ヶ谷宿の起源 2-3 桜ケ丘にあった神明社 2-4 交通路の大変化(戦国時代)−(後期鎌倉道) §3 戦国時代の桜ケ丘−加賀屋敷と抜け穴 §4 旧々東海道 §5 江戸時代の桜ケ丘道−相州道−助郷の道 §6 桜ケ丘の開発 まとめ 保土ヶ谷付近の街道の変遷図 |
 2005年 岩中前 |
| まえがき 保土ヶ谷の歴史といえば、どうしても東海道保土ヶ谷宿の歴史に限られてしまう。 「保土ヶ谷宿だけが保土ヶ谷ではない。東海道以外の地区の歴史があってもいい」という声はずっと以前からあったが、なかなか実現しない。この「桜ケ丘の歴史」はそれに挑戦したものである。 基本になる文献資料が何もないところから出発し、ゼロから創り上げる苦しさと楽しさをたっぷり味合うことが出来た。 1990「桜ケ丘の歴史」、1992「桜ケ丘道」として仮製本したものをもとにホームページ用に入れてあったが、今回新しい写真や図像を加えて大幅に書き直した。 2011年6月 |
|
| 桜ケ丘の歴史
通説 海面の低下(海退)にともなって、保土ヶ谷周辺の交通路が次々変化し、桜ケ丘の役割が時代によって変わってくる。 |
|
| 1.縄文時代の海進 縄文時代の海は関東平野深く侵入していた。 平地部分はすべて海で、古代の住居はすべて丘の上にあった。桜ケ丘や仏向に住居跡や土器石器が大量に出土。 |
2.鎌倉時代の鎌倉道
(前期鎌倉道) 海が引いて平地に住めるようになったが、帷子川下流はまだ海の中で、渡河点は和田。鎌倉時代の鎌倉道は山の上を通っていた。桜ケ丘に神明社が建立され栄える。 |
| 3.戦国中期、交通路が大きく変化
(後期鎌倉道) 海退が進み、交通路が海岸沿い/川沿いに移る。 古町橋が通行出来るようになり、後期鎌倉道が開ける。 山上に神明社が取り残されてさびれる。 |
4.江戸時代 旧々東海道と旧東海道新道 鎌倉道を一部利用して旧々東海道制定→神明社移転。 さらに、東海道新道→新町→権太坂開削。 江戸後期、桜ケ丘道は助郷の道として、通行量が増える。 |
| 5.桜ケ丘の開発 江戸時代〜明治の桜ケ丘は、森とイノシシが出る畑で、人は住んでいなかった。 大正時代、岡野欣之助の手で桜ケ丘の住宅地が開発が始まり、関東大震災をはさんで、昭和4−5年頃から住宅が建ち始めて現在の姿につながる。通称「桜ケ丘」と呼ばれていたが、昭和15年の地名変更で正式に「桜ケ丘」となった。 |
|