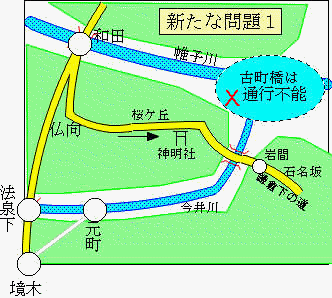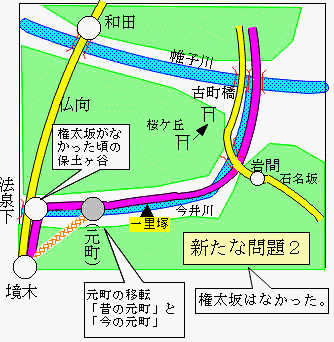| 保土ヶ谷付近の交通路 学説の変遷 目次へ | |
| 1.これまでの学説 昭和始めの混乱のままである。 | |
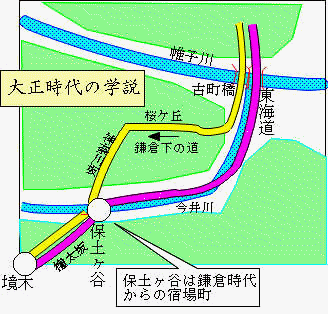 |
大正時代の学説 次のように言われていた。 鎌倉時代の鎌倉道は、古町橋を渡り、桜ケ丘に上って神奈川坂から保土ヶ谷宿(元町)に出ていた。 東海道も一部が山すそに移ったほかは、ほぼ同じルートを利用して保土ヶ谷(元町)に出た。 (武蔵国風土記稿、相模国風土記稿はほぼ同じような考えで書かれており、それを継承している。) 石野 瑛 横浜近郊文化史(昭和2) この説であれば保土ヶ谷は鎌倉時代以来、数百年続いた古い宿場ということになり、東海道はそれをそっくり利用しただけということになる。 |
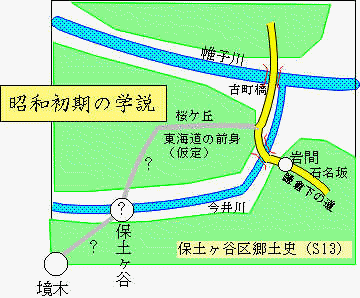 |
昭和初めの学説 鎌倉道の研究が進んで、鎌倉道は石名坂を越えていたことが分かり、学説が突然変わった結果、保土ヶ谷宿だけが取り残されてしまった。 石野 瑛 横浜市史稿1政治編(昭和6) これでは東海道は鎌倉道とは無関係なルートに設定されたことになり、保土ヶ谷宿の起源が何も分からないことになってしまう。 保土ヶ谷区郷土史(昭和13)では、やむを得ず鎌倉道とは別に保土ヶ谷宿を通る街道があったとしても不思議はないということにし、このルートを「古東海道(東海道の前身の道)」と名付けて、保土ヶ谷宿の成立を説明しようとした。 しかしこの道はつじつま合わせのための「想像」だけの道で、この道があったという資料の裏付けは何もない。 現在の保土ヶ谷前史(東海道以前の保土ヶ谷)はこの昭和13年の段階にとどまって、以後まったく進んでおらず、「保土ヶ谷宿の起源」について何一つ説明できないままになっている。 |
| ★保土ヶ谷区郷土史(S13)でいう「古東海道」とは、旧々東海道ではなく、上記の「東海道の前身」という意味に使っている。 すなわち旧々東海道より前の江戸以前の街道のことを言っているので間違えないように注意。 今となっては内容も完全に間違いだが、用語としても不適当で混乱に拍車をかける原因になっている。 |
|
| 「古東海道」の用語は「古代東海道」すなわち奈良/平安時代の東海道(公道)の意味で使われることが多い。(もちろん保土ヶ谷にはそんな道は通っていない。) 保土ヶ谷史では「旧々東海道」より古い「古東海道」として使っているのだが、意味を理解している人はほとんどなく、「古東海道=旧々東海道」と誤解して勝手に納得しているようである。 ★神明社前十字路の道しるべ「古東海道」は不適当であるが、「旧東海道旧道」「旧々東海道」「古町街道」「鎌倉古道」であれば、どれでも問題ない。 |
|