| 目次 | 保土ヶ谷の古道 鎌倉古道について 石名坂 追分け 相州道 大山道 今井の鎌倉道 太田道潅時代の交通路 ぐみゃうじ道を探る |
まづ下の図をクリックしてみてください。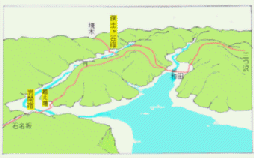 |
| 保土ヶ谷宿の成立と交通路の変遷 保土ヶ谷目次へ | |
| 東海道成立以前の保土ヶ谷交通路および保土ヶ谷宿について総合的にまとめた。 これまでの保土ヶ谷郷土史ではこの部分の研究がすっぽり脱落している。 何故、保土ヶ谷の地に宿が成立し発展したかという基本的な理由についても謎のままであった。 |
|
| これまでの定説との違いを示すキーワード (1)古町橋は通れなかった。(2)権太坂はなかった。 (3)「昔の元町」と「今の元町」。 |
保土ヶ谷付近の交通路の変遷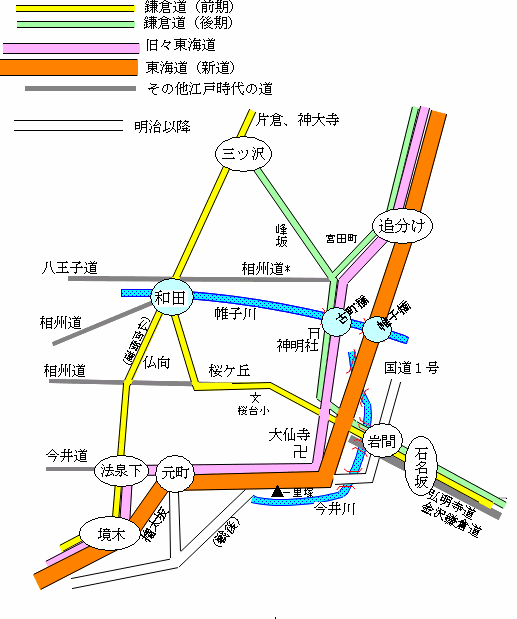 権太坂が出来たのは江戸時代のかなりあと(万治3年 1660)。それまでは法泉下が保土ヶ谷宿(昔の元町)。 鎌倉時代の古町橋は海中。古町橋が通れるようになったのは戦国中期で、それ以前の渡河点は和田橋。 |