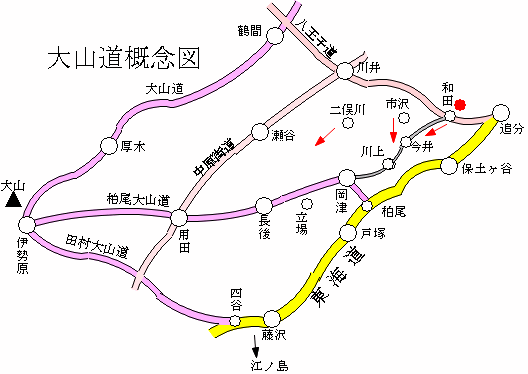 |
主要大山道 大山道としては、左図のような道があった。 ★下鶴間経由の大山道(江戸から大山へ参る本道である。) ★藤沢の田村大山道(大山登山の帰りに江ノ島へ寄るのに使われた。) ★柏尾大山道(戸塚手前の下柏尾の不動堂で東海道と分かれる。) 柏尾-岡津-長後-用田-伊勢原 保土ヶ谷付近では柏尾で東海道から分かれる「柏尾大山道」がもっとも近い。 保土ヶ谷の大山道はこの「柏尾大山道」のどこかに出る近道と思われる。 ★中原街道も大山道として利用できたはずだが、「大山道」と呼ばれたことはない。 |
||||||
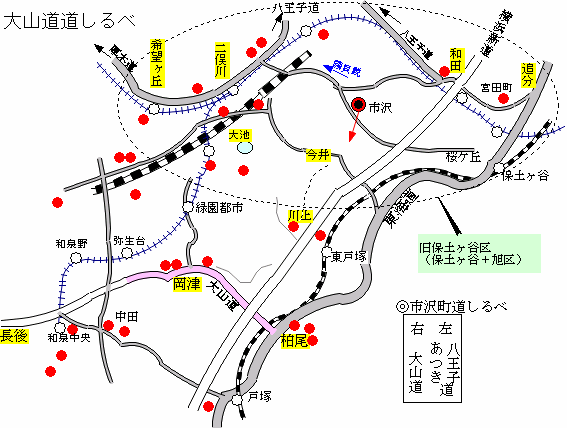 |
保土ヶ谷付近の道しるべについて 藤橋幹之助氏の労作 「道標とともに-金石碑」をベースにその後の研究も含めて「大山道」道しるべの一覧表とその場所を図に示した。 ほとんどの道しるべについて疑問点はなく、保土ヶ谷分だけが未解決である。 磯貝長吉氏は遺稿「土に探す」で、和田の大山道は二俣川経由の「和田-坂本-市沢-二俣川-岡津」のルートであり、二俣川駅近くの万騎ケ原の公園にある「大山道」道しるべの付いた庚申塔と「保土ヶ谷」「岡津道」の道しるべ石碑につながるとの考えを示している。 磯貝説の問題点 1)この二俣川コースは北寄りに大きく迂回するコースである。追分を起点に考えると下柏尾経由の本来の大山道よりかえって遠回りになる。 各地に「大山近道」を示す道しるべがあるが、必ず最短距離の近道を示している。「大山道」の道しるべに従ったらとんでもない遠廻りをさせられたということだけは絶対起きない。 |
||||||
| 2)磯貝氏は保土ヶ谷区(当時旭区を含む)の金石碑を全調査し、その中で上記の考えを示された。 上図の点線枠だけを眺めれば、二俣川周辺に大山道道しるべが集中しており、磯貝氏の推定は至極もっともである。 ところがその直後の追加調査で、市沢町518番地の稲荷社に◎の道しるべ庚申塔が発見された。 公道ではなく農家の庭先に通じる私道脇の稲荷社境内にあったため、同氏の最初の調査から漏れたものであろう。 「左 あつき・八王子道 右 大山道 」 「厚木・八王子道」は二俣川への道のことであるから、この位置から大山道は二俣川とは正反対の方角にあることを示している。磯貝説に対する真っ向からの否定の材料である。この地点で二俣川と正反対の方角には今井へ行く道しかない。 3)磯貝氏は(保土ヶ谷区+旭区)の金石碑を全調査したが、戸塚区の調査はまだやっていなかった。 今井から一山越えた東戸塚西口に大山道道しるべがあることが考慮されていない。 ①東戸塚駅の保土ヶ谷寄りJRトンネル付近の北天院の双体道祖神の前の線香立てに「おおやまみち」の文字が見られる。 ②東戸塚西口の川上町熊野神社の地神塔には「右 二俣川道、左 大山道」の道しるべがある。 (偶然かも知れないが、境内に建てられた新旧の石碑によると、この熊野神社の氏子には「大山」姓が非常に多い。) |
市沢町道しるべ  |
||||||
| 大畠説 以上から、筆者は保土ヶ谷付近の大山道のルートを次のように推定した。 追分-和田橋-仏向-今井-(ゴルフ場付近)-川上村(東戸塚西口)-岡津 このルートに旧道はほとんど残っていないが、ほぼ横浜バイパスに沿ったコースなので、地図上でたどるのは簡単である。 今井-川上間のルートは、これまでの地元郷土史では「今井の鎌倉道」とされていた道である。 (この旧道も環状2号線工事で完全に消滅した。) 今井鎌倉道についても筆者に異論があり、根本的な見直しが必要なので、別項で合わせて論じる。 今井鎌倉道へ
|
川上町熊野神社の道しるべ |
||||||
| ★磯貝氏「土に探す」の扱いについて 「土に探す」は病に倒れた磯貝氏が後輩のために未完成の研究や研究テーマを書き残して頂いたノートを出版したものであり、完成された研究ではない。(磯貝説などと軽々しく引用しない方がよい。) 研究報告というよりも「保土ヶ谷にはこういうテーマがまだ残っているので後はよろしく」という後輩への宿題として受け取って、後輩の手で完成させるべきものであろう。 「土に探す」のまえがきで磯貝氏が繰り返し「自信がない」といっているのは未完成の内容であることを読者に注意しているのであって謙遜で言っているのではない。同氏が決して謙遜な方ではなかったことは周知の事実である。 |
|||||||