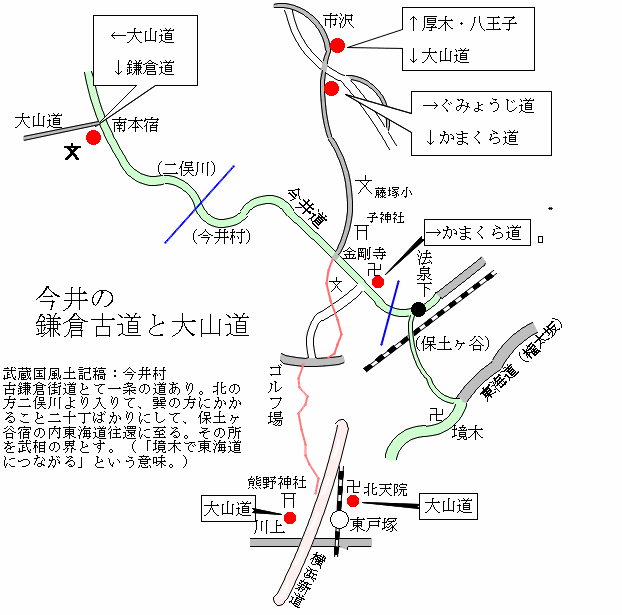| 今井の鎌倉道 目次へ |
| 保土ヶ谷戸塚周辺の道しるべについては藤橋幹之助の「道標とともに-金石碑」(昭和57)がある。 藤橋氏は地元の研究家で、退職後、「道しるべのついた石碑石仏」の所在地と碑文碑姿の調査に半生を費やされた。 同著には169の道しるべが記載されており、うち31に「鎌倉道」の文字が彫られている。 同著から鎌倉道石碑を鎌倉道の概念図上に書き込んだものを図に示した。 |
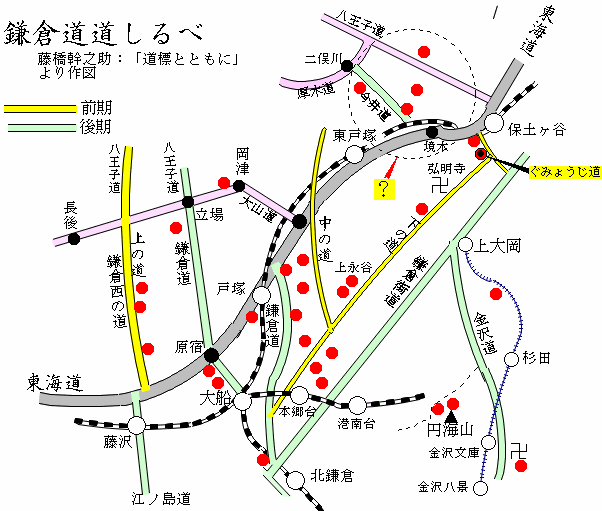 |
| 保土ヶ谷~戸塚付近の鎌倉道は大変混み入っている。 黄色が鎌倉時代からの前期鎌倉道、緑が戦国中期に開けた後期鎌倉道である。 鎌倉時代以来の三本の「鎌倉古道」(上の道、中の道、下の道)と、その後開けた江戸時代の「鎌倉見物の道」が数本、さらにそれぞれの枝道が走り、鎌倉に近いこの地域に集中し交錯しているため、個々の道しるべがどの鎌倉道を指すのか分かりにくく、地元でも混乱することが多いが、この図で鎌倉道と石碑の関係が一応整理出来たつもりである。 保土ヶ谷付近の4基の道しるべだけが、どこへつながるのか、まだ解明されていないことになる。 |