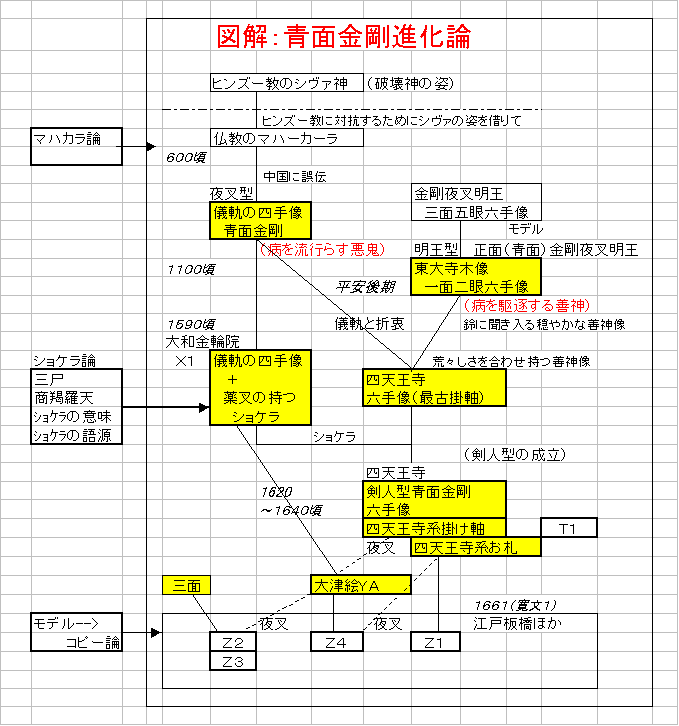| 剣人型青面金剛の成立 2000/11/1 大畠 目次に戻る 江戸時代の少し前、太閤秀吉の晩年時代(1590〜1595頃)に「夜叉がショケラを持つ儀軌四手像」としてショケラ(女人像)が生まれた。 また「江戸時代のかなり早い時期(1640以前)に、ショケラを持つ六手剣人型青面金剛が生まれ、四天王寺のお札や掛け軸として固定し、全国に広まった。 以下、青面金剛展カタログなど残存する古い青面金剛像を参照しながら、剣人型青面金剛の成立について大胆に推定した。 |
|
| 1.平安時代の末、「素人でも礼拝できる穏やかな善神像」が求められ、金剛夜叉明王(三面五眼六手)の姿から正面金剛夜叉(明王)の六手像(一面二眼)が作られたことをすでに述べた。 しかしこの像は次の二つの点で問題があった。 ●金剛夜叉明王の中二手は、鈴と鈷を持っているのではなく、鈴と鈷を使って「金剛薩多の威儀」という印を結んでいる。(弘法大師像なども同じ印) 鈴と鈷をバラバラにして持ち替えたり、鈴を鳴らしたりさせたのは儀軌から見ておかしい。 ●「穏やかな善神像」という注文にこだわったため、目を半分閉じて鈴の音に聞き入るやさしい姿になったが、これでは凶悪な病魔(伝染病)に力で対決する役割としては穏やか過ぎて力不足である。 |
 |
| 2.その後の青面金剛は原型の儀軌四手像の荒々しさを一部取り入れて折衷した六手像が主流になった。 (いざという時、昔の刺青を見せる「遠山の金さん」型ヒーロー) こうして出来たと思われる古い青面金剛の掛け軸が四天王寺に残っている。二童子の衣裳(細いズボン)や持ち物(箱)から古い時代のものと推定できる。持ち物は三叉戟、輪、弓と矢で、中二手は何を持っているかよく分かないが、ショケラではない。(青面金剛展カタログ) また青面金剛展カタログ表紙の厨子に入った六手青面金剛木像はこの時期の系統らしい古い様式である。 (二童子の衣裳と持ち物(小箱)が古風)。 六手の持ち物は三叉戟、輪、弓と矢、金剛鈴と金剛鈷である。 |
|
 |
 |
| 3.一方で儀軌四手像をそのまま作ることも行われており、前記のように秀吉の家臣だった片桐貞隆は眷属の四夜叉にショケラを表す女人像を持たせるという工夫をした掛け軸(X1)を所有し信仰していた(1597以前)。
|
 (写真はX2で代用) (写真はX2で代用) |
| 4.X1で創造されたショケラ(女人像)を四天王寺の古い様式の青面金剛本尊の空いている中二手に持たせたることで剣人型青面金剛が生まれ、早い時期(1640以前)に四天王寺系お札や掛け軸として全国に広まった。四天王寺系のお札や掛け軸のデザイン(二鬼や四夜叉のポーズや持ち物も含めて)は初期に固定し、江戸時代を通じてほとんど変わっていない。 小泉庚申堂(1640頃)が建てられたとき、本尊掛け軸X1は儀軌四手であるにもかかわらず、「お前立ち」として用意された木像(T1)はすでに剣人型であった。 |
|
 |
 |