 一歩から
一歩から 7次宿場 平塚 江戸後期1843年 男1106 女1008
平成男130439女128100
海の入り江にある馬入川に到着した。源頼朝が橋の上で落馬し馬が川に落ちた故に
馬入川と名前がついたらしい。牛なら牛入川だったのかな。ウッシウッシなんてね。
午後の陽射しの照りつける国道は車の往来が激しく熱風をまいている。
日陰の微風がとても爽やかで針葉樹の有り難さを実感する。
空は子供が描く絵のように雲がふんわりと泳いでいて、スカイブルーが眩しい。
平塚に到着しました。次回は芝居で有名な「番町皿屋敷」お菊の塚がある
平塚駅前公園からのスタートになります。
平塚宿
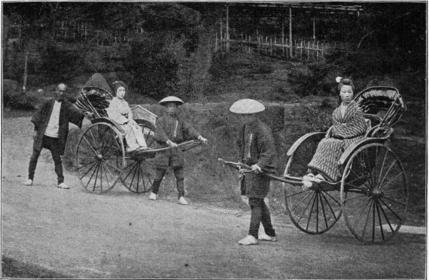
平成9年5月10日(晴れ)平塚〜国府津(6回目)
平塚駅を降りて商店街を抜けて国道1号線に出る手前の日本そば屋に入り
腹ごしらえしてから、出発する。ところで蕎麦も江戸と関係していて、
漆器は、英語でjapanlacquerと言うくらいで、元来は幕府・大名・裕福な町人などの
特権階級の調度品で日本を代表する器であるがそば好きの江戸っ子達のおかげで、
漆塗り湯桶が庶民でも手に入るようになり,庶民の暮しに根づいたそうです。
粋な食べ方もあるようだが、私は汁一杯付けて食べるのが好きだ。
平塚宿と書かれた標柱の前に立って写真を写す。
当初は、照れや恥ずかしさがあって、人が居なくなるのを待って「早く写せ」と
言ってたのですが今はまったく平気になりました。
良い思い出を残す為にもどんどん撮らなくちゃ!。
ママのカメラの腕が格段に上達していて、プリントを並べると違うのだ。
悔しいから褒めたりしないが
俺も良い写真を撮るぞー!(心の叫び)この区間は国道1号線が、
そのまま旧東海道である。
花水橋を渡って右側の国道沿いに藁葺き屋根の民家があり、洗濯物が
風になびいているので、生活の臭いがする。どのような方が住んでいるのか。
私は岩手の山村生まれで本家も藁葺き屋根でした。
6歳位の時に、屋根の葺き替えを、村人が集まって作業していたのも
少しだが記憶してます。実際に生活していた体験は、親戚のなかでも私の世代までの
記憶が、最後になるかも知れませんね。ここは道路隔てて向かいに
善福寺があるので、後々建替えても元の場所を知ることが出来ます。
藁葺き屋根の民家 鴫立庵


8次宿場 大磯 江戸3056男1517女1498
平成32748男15966女16809
江戸時代からの松並木を歩く。途中で切り株に400年前300年前200年前と
年輪に表示がある。この太く背の高い松は家康で、こっちは吉宗の頃に
植樹されたのかと比較が出来て感動を覚えた。
すぐ隣は国道1号線で車が猛スピードで往来しているが、
歩道は、この松のお陰で穏やかな雰囲気と静粛な空気が流れている。
鎌倉時代は遊女が多くて化粧坂(けわいざか)と
呼ばれてた地帯を過ぎて、しばらく行くと小川の脇に鴫立庵がある。
西行上人が東路行脚の時、このほとりの沢辺を通った時に詠んだ一首で
「心なき身にもあはれはしらけり 鴫立沢の秋の夕暮れ」とある。
有料なので入りませんでした。国道から、伊藤博文の屋敷跡の
横を通り過ぎて約5分で日本最初の海水浴場、大磯の海岸にでた。
(湘南発祥の地大磯の由来の看板あり)きらきら輝きながら
寄せては返す波。波の音が気持ち良く沁みる。中国料理の
槍浪閣(そうろうかく)伊藤博文の旧居で食事 ラーメンと言えども
高価でした。味に触れるのはよそう。閣下に申し訳ないから。
しかし財布が軽くなったのが痛い。しばらく行くと、ガソリンスタンド裏に、
西長院と言う寺が有る。切道地蔵(きりとおしじぞう)の名を
「お化け地蔵」とか「身代わり地蔵」と呼ばれていて、ここを通る旅人の
身代わりになって切られ、血を流し、其の時の切り傷が身体に
あるという。残念なことに、現在この寺は、かなり荒廃している。
地蔵様も仕事終えて休んでいるのだろうか。また国道と一緒になり、
黙々と歩いた。梅沢地区の宿屋は海岸で取れるアンコウ料理が
名物だったらしいけど、本場の名物と云われるアンコウ食べてみた〜い。
この付近は左に海を見ながら、心持ち良い風、波の音、潮の香りが
流れて、背中を押されるように進んで行けます。
やっと国府津に到着。夫婦で旅できるのも留守番してくれる、
おばあちゃんがいるからだと感謝しながら電車に揺られて帰ります。
槍浪閣(そうろうか 身代わり地蔵


平成9年年7月5日(晴れ) 国府津〜箱根湯本(7回目)
国府津駅前食堂で、朝食をとる。ママが冷やし中華で、私はレバ炒め定食を食べる。
毎度のことだが体力付けてからの、スタートです。
出発して、大山道入り口の道標を通り過ぎると、ほどなく眞楽寺がある。
マリア観音(幼児のキリスト抱いている。)があり切支丹禁制ゆえ文殊菩薩と
偽り秘仏にしていた。おばさんが出てきて団体の予約に見せていると説明受け、
拝観出来なかったのが残念でした。
東海道歩いていると言ったら、こんなに着て暑い中大変ねと、ママが言われました。
日除け用に長袖のヤッケを着ていたからでしょう。 暑い!あつ〜い!。
野球帽だけでは日除けにならないので、ママが麦わら帽子を買った。
良く似合う!「どこの百姓の嫁だべや〜。めんこいごっ」私は日焼けしたいので
帽子を後ろ向きにして、お天道様に顔向けて、堂々と歩く。風が出てきて突風に
飛ばされそうになったり、前に進みづらくなったりと小1時間苦労した。
風がやんだころ酒勾川(さかわがわ)に着いた。
題名が酒匂川という股旅演歌があるので覚えようとCDまで買ったのですが、
なにせ音痴なので諦めました。持ち歌にしたかったなぁ〜。
いよいよ日本橋を発って以来の、初めての城下町です。
城下町とは大名の居城を中心として発達した町です。
これから先の旅で沢山のお城が見れるので、とても楽しみです。
旧街道


9次宿場 小田原 江戸5404男2812女2592
城下町 平成196274男95726女100548
大久保加賀守
大久保加賀守11万3129石の箱根の守りに任じた大藩である。
雰囲気の残る旧街道、旅館街の路地をくねくね行くと、小田原の総鎮守となっている
松原神社があった。ここで一休み!旅人の?特権で(勝手に)
境内で靴を脱いで横になる。
仰向けになり、空を見ればゆっくり流れる雲、高木を揺らす風音、緩やかな睡魔が・
このあたりが、弥次さん喜多さんの五右衛門風呂の騒動があった宿場町らしい。
小田原城は何度も来ているので寄らず、旧街道を進むと大久保寺に着く。
ここは小田原城主、大久保忠世の墓がある。寺で草むしりをしている人達のだろう
冷たい麦茶を、参拝する人達の為に用意していると勘違いして堂々と飲むママ。
「その麦茶、草むしりの人達のじゃないの」
「えっ〜飲んじゃった!」
遠くで作業している4〜5人の姿が見える。果たして真実はどっちだろう?
緩やかな坂を登り後は川に沿って歩く。入生田駅があって左手に見える山が、秀吉の
小田原攻めの一夜城で知られている石垣山。急な斜面で、川からもかなりの高台になる
良く城を造れたと感心させられる。後、湯本まで2キロ位のところから、ペースダウン!
ママが今日履いてきた靴が合わないようで、太ももや足首まで張ってきたので
(保土ヶ谷で購入)スプレーをなんども吹きつけ、時々路上の脇で休息取りながら。
国道と別れて旧街道を歩いていたら、夏みかんの木が沢山の果実を実らしており、
「食べてくれ。ビタミン補給して元気になれ!」と言っている気がします。
元気取り戻し一気に湯本に到着。
「せっかくだから温泉に入ろうよ」「いいわね〜」で即決まり。
旅の目標を達成した疲れを露天風呂温泉で癒して帰れるなんて至福の極みだ。
箱根湯本 畑宿


平成9年9月20日 (晴れ)箱根湯本〜芦ノ湖 (8回目)
10次宿場 箱根 江戸844男438女406
平成13270男6408女6802
今回の旅は、初めて一泊二日の日程です。
湯本スタート10時、芦ノ湖まで16時に到着予定。
翌日は、早朝出発して三島まで行く予定です。
小田原宿から三島宿までの8里(32キロ)を箱根8里と言うが、
今回はその後半にあたる東海道最大の難所を、昨日購入の大型のリュックに今夜の寝る為に
使用する簡易テント等を詰めこみ、走破に向けて、意気軒昂に出発。
湯本駅から少し戻り三枚橋から旧街道に入る。いきなり登り坂になる。旧街道の静かな町並が
続き左側に銭湯があるので覚えておけば
いつか役にたちそうだ。そして右側の急な斜面を下るのだが、小さく旧街道と標識があるが
注意しないと通り過ぎてしまいそうです。

