 一歩から
一歩から  桑名宿〜草津宿
桑名宿〜草津宿 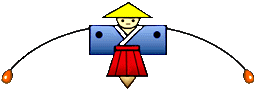
平成男70046女72301
城下町
松平下総守
桑名は蛤の名物であると、情報を得ていたので、食事は桑名でと決めていた。
どうしても食べたいので旧街道からそれて桑名駅前に行き商店街をぶらりぶらりすると
商店街出口の交差点角に「名物 はまぐり】の暖簾がしっかりと見えた。
1680円だったと思うが蛤御膳を食べました。美味しかったです。
しばらく行くと、えっと思うほどの歓楽街がありました。城下町の名残でしょうか?
今はない桑名城ですが、三方を海に囲まれ、扇城とも呼ばれた
美しい城であったらしいが、藩主松平が幕府方で戦ったので、明治には
落城してすっかり荒れたらしい。今は市民の憩いの場、公園になっている
旧街道沿いに四日市富田小学校があって、小学校入口に石碑【明治天皇駐輦跡】
とあります。
この場所は旅館跡でちなみに、明治天皇はここで焼き蛤を食べられたそうである。
小学校では歌の夕べを開催するらしく男女沢山の人が入って行きま
割り箸袋


43次宿場 四日市 江戸後期1843年男3522女3592
平成男15519女157337
四日市宿に入るとすぐに、十字路の交差点角に【日永の永餅】の
大きな看板があります。
笹井屋創業天文十九年(1550)だ。永餅とは牛の舌餅と呼ばれるように
少し細長くあんこが入っていて表面にすこし焼きが入っている。
甘からず丁度よい味です。妻がお土産に沢山買いました。
采女町(うねめと読むが天皇の食事のお世話をする女官)の事だと、
町が発行した資料にある。新しい家の前をくねくねしながら通って行くと
杖衝坂に到着した。
芭蕉が「歩行ならば杖衝坂を落馬かな」と読んでいる程の急坂です。
明治の頃と思われるが、着物で、草履で、腰の曲がった婆さんが坂を登って
行く写真があって、当時の様子が良く分かるけど、
私の遠い記憶(幼いころ)とも重なり心が折れそうな写真だ。
杖衝坂



平成20年4月29日 (25回目)
44次宿場 石薬師39232歩
平成男868女821三重県鈴鹿市加佐登
河曲の駅前からいよいよスタートだ。河曲駅は無人駅で駅前広場と
公衆トイレがあるだけだった。
歩き始めて30分やっと人に会えた。ゴミだしで一輪車に家庭ごみを積んで
運んでいるおじいさんだ。
思い起こせば、うちのおじいちゃんも、良いからと言っておいても、
朝早くせっせっと捨てに行っていた。
自分の仕事だと思っていたらしいのだ。思い出します。
田植えが真っ盛りで、新緑の芽が優しさを投げかけるなか
石薬師に向かい歩き始めます。
一号線左側の木々に囲まれた中に石薬師寺あり。
久しぶりの東海道の旅が石薬師寺からなので
偶然とは思えない廻りあわせを感じます。ひっそりとした佇まいに無駄な
飾りのない風雪を耐えてる御堂。お線香を立て、旅の安全と家内安全を
願い手を合わせた。広重の五十三次の浮世絵の中の風景そのままの
田園風景を進む。右の国道一号線は車の往来激しい現代社会です。
街道から脇道にそれ、国鉄加佐登駅を通り過ぎた所に『日本武尊』を葬った
白鳥塚(陵)あるらしいが、寄らずに先を急ぐ。
鈴鹿川と平行してしばらく歩くと庄野宿に入る。
河曲駅 石薬師


45次宿場 庄野 江戸後期1843年855男413女442
平成男2092女2020鈴鹿市庄野東〜羽山
川俣神社を通り過ぎて、安楽川と鈴鹿川の合流地点は
水害で苦労したところで、村人が堤防の構築を神戸藩に願ったが、
南岸の城下に水害の恐れありとの理由で許可ならず。そこで村の女たちが
女なら捕らえられても罪が軽いだろうと、役人の目を盗んで堤防を築いた。
女たちは一旦捕らえられたが無罪となり、むしろ功をねぎらって
絹五疋と金一封を与えたという。
歩道のアスファルトの割れ目から種を蒔いたかのように
沢山の黄色い花が咲いている。当時の女達のように襟を伸ばし信念を
貫く強さを見せられているようである。井田川町を通り過ぎて程なく
国道306号線角に マクドナルドが有ったので休憩をとる
時刻は9時40分なので4時間以上も歩き続けた。
実はウオーキングシューズをお揃いで新調したのです。
足元の不安が無いことの安心感は疲れまで
決して高くないが値千金の価値がありました。
水田


46次宿場 亀山 江戸後期1843年男790女759
平成男1235女1377三重県亀山市東町本町野村町
城下町
石川日向守
江戸口門跡がある、ここから亀山宿に入る。
旧街道から亀山城跡の多門櫓を遠望できる場所は、お堀があって
街道沿いに立ち並んでいる大きな屋敷の裏側が見れる珍しい体験が
出来る場所でした。
近くに1865年亀山藩武芸指南役山崎雪柳軒が開いた亀山演武場がある。
明治以後も私財を投じて指導したが、武道精神高揚という志を
世に容れられないまま、明治26年切腹した。
江戸〜明治と生き抜いて武士としての誇りを一途に通したのだろう。
野村の一里塚は樹齢400年をこす大きな椋の木(むく)が威風堂々としている。
椋の木、の隣にある家が、業者を呼んで屋根の葉っぱの撤去に追われていた。
大変な出費であろうと想像するが、いつまでも椋の木を保存して戴きたいと思う。
『関の小萬のもたれ松』の案内板がある。
説明によると関の宿の小萬が敵討ち修行のため亀山に通う途中、
からかう若者を避けるためにこの松に隠れたという伝説の場所である。
修行に向かうのに一ヶ月草鞋25足消耗したという。
私たちは亀山演武場近辺通過が11時頃で今12時50分なのでやく、
2時間かかったので15歳位の娘、小萬は起伏多い山道を片道約2時間かけて
通ったことになるので、辛いけど宿命と割り切っていたのか?
亀山宿入り口 亀山


47次」宿場 関 江戸後期1843年男1008女934
平成男2755女2765亀山市関町新町中町木崎
旧東海道の中で、1・2を競う人気のある街道に到着した。
旧町並みの入り口に案内板があり、
皆さん記念写真に夢中である。途中に誰でも入れるようにと
開放された旧家に入った。
2階から眼下に広がる景色は時代劇のセットである。
たまたま若い子供連れの親子が居たので
写真を撮ってあげた。『関の戸』昔からの銘菓で、1624年から現在
12代目の老舗で、店先で立ち止まっていたら「ここの菓子はおいしいですよ」と
声をかけて通り過ぎて行く人がいた。
この街道は確かに古き時代の平屋の建物が多く軒下で隣
奥さんとの会話が聞こえてくるような、今で言う癒される雰囲気の町通りである
地蔵院の真向かいにある会津屋で食事を取る。
偶然だが先の小萬の関係する場所であった。
「久留米藩士小野元成に殺された牧藤左衛門の妻は、
仇を尋ねて身重の体で関まで来たが旅籠山田屋で女子を産んで亡くなった。
山田屋の主人は、この子を小萬と名付けて養育、亀山藩の
加毛寛斎の許に剣術修行に通わせたが、
小萬18歳の時に仇を発見、本懐をとげた。
そのあとお礼奉公して1803年に38歳で亡くなった。」のが会津屋の近辺である。
関宿入り口 関宿薬屋


平成20年4月30日 (26回目)
29802歩
48次宿場 坂下 江戸後期1843年男272女292
平成男27女78三重県亀山市関町坂下
2013年4月30日(火)雨後曇り
緩やかな坂を下り国道に出てしばらく歩き右側の弁天橋を渡る。
右側は筆捨山で左側は鈴鹿川である。
まさに旧東海道の趣きです。奇跡のオムニバスと叫びたい。
濃霧が発生したら、歩くのも危険かもしれない。
木々に囲まれて真夏でも日陰になり涼しいだろう。
向かって左側に家が立ち並び始めた。突然広場のような場所に着いた。
峠が雨で越せないときは大いに賑わった宿場である。
現在も筆捨山を背に大勢の住民が住居を構えている。
四季折々の鮮やかな色彩と共存し、
川から奏でる悠久の音色聞いて生活して居るのでしょう。
鈴鹿峠 鈴鹿峠入口 左側


ここから先は家も無くなり「鈴鹿山は八丁二十七曲にして道狭く険しい。
清水所々湧き出て、雨の日は超えるのは無理だ。」歩道を歩いていても
直ぐ横を通過するので危険な場所で
276メートルの長いトンネル】と記事で読んだ事があるし妻も一緒だし
(俺一人なら挑戦?)と言う訳で引き返す事にする。
会津屋の店員にタクシー呼んで帰る人が多いですよと
教えられていたがその通りになりました
49次宿場 土山 江戸後期1843年男760女745
平成男4245女4223甲賀市土山町
田村神社に寄った。遠くから望めばただの森だが近くによると
伐採されて整っている林の中に参道が延びている。
神社は現在修理中?テントがかけられていたが厳かな雰囲気がありました。
街道は歩きやすい材質で舗装されていてウオーキングには優しい町です。
ひっそりした町並み、古民家も多い。
平坦で真っ直ぐ続く町である本陣後の隣にある家は重厚な雰囲気の
連子格子造りの広大な邸宅で柱から、梁から屋根まで見事である。
土山本陣跡


50次宿場 水口 江戸後期1843年男1314女1378
平成男20460女20340甲賀市水口町
城下町
大岡山が、1585年秀吉の家臣中村一氏が築いた岡山城があった城下町。
今は時間が止まっているような、静かな町で専業農家の息吹が聞こえる街道である。
新しいバイパスは上下線とも激しい通行量だが旧街道は生活道となっており車は少ない。
きょろきょろして歩く私でも危険を感じないほどである。特に今回の徒歩での行程は昔ながらの
佇まいがひっそり生きているので末永く守り伝えたい日本文化の町だと思う
旧街道 旧街道


平成25年5月1日 (27回目)
51次宿場 石部25405歩
江戸後期1843年男808女798
平成男4105女4186湖南市石部東・北・西・中央
田園地帯の村落が続く。豪農と呼ぶにふさわしい立派な家屋敷が続く。
庭の手入れもきちんとされており魅了される。
案内板のある和中散本舗跡の家も唖然とするばかりの迫力ある豪邸でした。
平坦な街道を過ぎると、草津線の線路に平行してしばらく歩くと石切り場を通り過ぎた。
古い地図に金山跡と記載あるので調べると金山銅を掘った山で、
堅い人間を「石部金吉」と呼ぶのが
この山から起こった言葉らしいが聞いたことない。
六地藏村に入ると六地藏神社がありました。参拝すると、かなり寂れている。
地名になっているほどの神社なので、もう少しなんとかしてと言いたくなるのだが、残念だ。
続いて「鈎里村」(まがりむら)を通りあっという間に住宅地になり
久々の商店街に入り一息付けそうで。
石部宿 和中散本舗跡


52次宿場 草津 江戸後期1843年2351男1172女1179
平成男69600女64960
草津駅近くの商店街で昼食を取る。
地域の名物で豪華に食事をと思っているのだが、
今日はラーメン餃子、昨日は盛りそばセットだった。
昼食は汁物が食いたくなるんです。
草津本陣後を過ぎたら、酒屋があったが通り過ぎて建物の横を見たら
奥が長く白壁の大きな建物だった。
これは造り酒屋に違いないと思い暖簾をくぐった。
女将さんと娘が応対してくれて、試飲を勧められ、
辛口が良いなどと生意気なこと云いつつ、俺はお猪口で3杯、
妻はお猪口で2杯を試飲したが皆香りが良くて結局、いい気分になり、
蔵出し本釀造2本購入した。
帰りがけに道灌名の酒が多いですが、関係有るんですかと尋ねたら
太田道灌の子孫ですとの事。
たまげました。今日一番の良い思い出が出来た。
案内文より【徳川三代将軍家光のころから、子孫が近江、草津宿の
目付けとして街道見張る役目を果たしていた。
廃藩後に酒造りを始め太田酒造「道灌とした】普通の町並みを歩く。
途中創設したての一里塚もありました。
今、太田酒造で入れ替わりに店内に入った男の人が私たちを追い抜いていったが
もちろん酒をぶらさげてた。約5キロ以上並走して来た事になる。
今日も良く頑張った。瀬田駅で終わりにする。建部神社
草津本陣 造り酒屋太田道灌


2013年5月2日瀬田駅から大津駅まで
勢田の唐橋は江戸時代は木造の橋で1979年にコンクリートの橋になったが凝宝珠は
歴代受け継がれており「文政・明治」などの名が現存する。膳所藩が管理していた。
勢田の唐橋を渡り街中を通り過ぎると、にぎやかな町に入る。
かなり年上のおばあさんに抜かれたが
我ら夫婦はいかにきょろきょろしながら、進んでいるか分かる出来事だった。
これでいいのです。
膳所城(ぜぜ)の城下町に入るが城下町の面影はないけれど、
100メートル毎に寺と神社があるようでとても多く感じられた。
旧街道も分かりにくく迷いうろうろしていると申し訳なさそうに
小さな看板があったりする。旅人にもう少し優しく案内してくれるとありがたい。
勢田の唐橋 琵琶湖


今回の旅の途中で足を伸ばして甲賀流忍者屋敷に行ってきた。
表から見ると平屋の茅葺屋根の一般的な建物、しかし3階まである忍者自身の
住居として現存する日本で唯一の建物なのだそうだ。
おばさんが良く聞き取れる声で説明してくれるので、楽しめた。
抜く道の襖を空けたとき忍者が隠れていたので
妻が「きゃー」おばさんが「その声が聞きたかった」とにんまり。
土産に白木の刀を買いました。

