 一歩から
一歩から  大津宿〜京都三条大橋
大津宿〜京都三条大橋 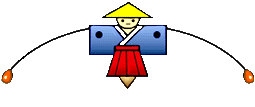
53次宿場 大津 江戸後期1843年男7306女7586
平成男女176114大津市
昨晩から大型台風27号が近づいており雨風が強いなか関西地方は通り過ぎると判断、
京都に向かいました。案の定、東名高速愛知県浜名湖インター近辺は大雨でした。
土曜日早朝7時大津市大津駅に到着、台風は京都を通り過ぎたようで曇り空である。
雨が降っても準備が万全なので今日はゴールまで必ず到着する決意です。
早速逢坂山を歩く、今は切通しが国道一号線になっており車の往来が激しいが
逢坂常夜灯が立っているのでこのあたりだと理解出来る。
逢坂山関は山の上にあったらしい。
(これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関)の歌碑がありました。
逢坂常夜灯


さらに旧道を行くとうなぎ専門の料亭【かねよ】があった。
大津宿走井茶店と五十三次に描かれている。
慶応時代創業の老舗だ。まだ早い時間なのに若い板前さんが
店先の支度をしていたので何時から営業と聞いたら10時からだと言う。
二時間は待てないので残念だがあきらめましょう。
歩いていて、がけ崩れの山肌が見えるので大雨か地震なのか怖さを実感する。
旧街道と看板が有る入り口から、賑やかな商店街になった。
それもそのはずでJR山科駅がありました。
商店街の出口にケーキ屋が有ったので、コーヒータイムにした。
二階の店内から山科の旧街道を写すことができた。
電柱が邪魔ですが雰囲気は出てます。
昔は牛が荷物を引くための引き石があった。
石が磨り減り線路のように二本の溝ができており
過酷さが感じられる。後世に残す為にモニュメントになっていました。
かねよ旧街道



疎水道
蹴上浄水場を通り過ぎると、運河の『疎水』が観れた。
京都は水不足で悩んでいたが、
琵琶湖から京都まで20キロの運河総工費一兆円かけて
明治23年4月苦難の末に『疎水』は完成した。
そしてついに平安神宮に到着した。鳥居の大きさに圧倒された。
京都三条大橋まで、もう一歩である。
子供たちと12時に待ち合わせをしているが世紀の瞬間が刻々と迫っている。
二条大橋通過した。次は三条大橋です。
平安神宮鳥居


54次宿場 京都三条大橋
到着しました。涙。涙のゴールインです。
人目をはばからずに三条大橋の真ん中で抱き合いました。そして万歳。


三条大橋
京都 (今昔東海道独案内 より抜粋)
1868年10月13日明治天皇は3300人で東京に行幸した。
この時に江戸城から東京城と名を変えた。
京都の人たちは天皇が東京に移るなどと露知らず、天皇も京都の人たちを
安心させる為に一度、京都に戻り、再び明治3年に東京へ行った『遷都』である
京都は御所という商いの得意先を失い美術品の流通もなくなり
伝統工芸も存亡に危機に直面していた。人口は三分の一まで減ったのである。
新橋〜横浜の鉄道が開通した以降全国に鉄道が敷かれたが、
これが旧街道筋に投げかけた波紋は大きかった。
鉄道が開通すると、歩く旅行者が減ると考えて、猛反対ついに他の町を通らせた例などがそれである。
こういう宿場町は、逆に便利な鉄道を利用する人たちに忘れられた存在になり、昔ながらのたたずまいで
ひっそりと生きているのである。たとえば御油、赤坂、坂ノ下、石部などがその例だろう。
又鉄道が通るにしても自分たちの商売に影響出ないようにと町の外周りを通らせたところもある。
ともあれ時代は変わる。文明の発展は絶え間ない交通の進歩をもたらしているのである。
(今昔東海道独案内 より抜粋)

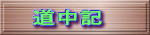 最終章
最終章