 一歩から
一歩から 平成8年4月28日(日曜日)快晴 日本橋〜平和島 (1回目)
日本橋
現在の日本橋は高速道路の真下で、橋の真ん中に元標があります。
1603年約400年前の様子が日本橋道路脇に当時の模写絵としてあり、
見るだけで当時の賑わいが想像できて同じ場所に居ることに心踊る。
危険承知で車が途切れたときに元標にかけ寄り歩道側より妻に写しもらう。
嫌がる妻に「いまだ〜いけ〜」と背中を押した。
この田舎者との視線を浴びても大切な記念写真ができた。
日本橋を基点にして一里塚(約3.9キロメートル)を設けたが
1844年には104の塚が現存してたが大部分が荒廃して無くなったらしい
これよりいざ出発!銀座(銀貨を作っていたのが由来)の歩行者天国の賑わいは
祭りそのものでテレビで馴染みの看板やブランド店があっちこっちにある。
大人達は洗練されているし、若者は自由な表現を謳歌している。
「立ち寄りたい店ばかり」と言いながら私たちはキョロキョロするばかり。
北町奉行所、南町奉行所の近くを通り、流行歌[銀座の柳]の歌碑の側にある、
かろうじて1本だけある細い柳の下で休憩とる。
浅野家の菩提所、泉岳寺(赤穂浪士・四十七士の墓)
あるが今回は寄らずに先を急ぐ。
江戸時代から明治になり約100年以上の時が過ぎているが、山を削り宅地にして
河川を埋めて道路にし、馬から自動車になり発展を遂げた東京は凄い。
江戸本によると(水売り)江戸時代、田舎から二人の青年が江戸の町に出てきた。
当時の江戸には水道がなく「水屋」と呼ばれた、「水」を売って歩く商売がありました。
一人の青年は「江戸と言う町はなんと住みにくい町だろう。
江戸はただのはずの水にも金を出さなければならない。」と江戸が嫌になり
すぐに田舎に帰ってしまいました。
もう一人の青年は「江戸という町は何と面白い町だろう。
水を売って金儲けの商売が出来る」と考えました。
このように江戸は全国から人が集まりプラス思考の人が成功を納めて
いったのでしょう。
明治初期の日本橋
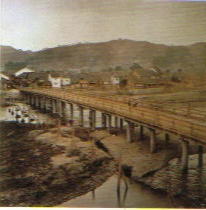

1次宿場 品川
江戸後期1843年 男3272 女3618
戸口調査は1843年東海道宿村大概帳によるデータ
平成 男179836女174850 現在の戸口は2012年と2013年
平成集計は市町村国勢調査の発表によるデータを参考にしたが概ねであるので注意。
娘の大学合格祝いで、家族で食事にきてゲーセンで遊んだ新高輪プリンス。
「ここで合格祝いの食事をしたんだよな。」と品川駅近くの喫茶店ルノワールで
休憩する。コーヒー1杯でふかふかのソファーに座れて
約30分靴も脱ぎ捨てグッタリする。
涙橋(鈴ヶ森刑場に送られる罪人と家族が別れの涙を流した橋)を複雑な
気持ちで渡り過ぎて行くと程なく鈴ヶ森刑場がある。無刑囚(死刑でない刑期)は、
一日殆どボーッと過ごすが、死刑囚は、少ない時間精一杯生きようとするらしい。
当時の死刑の判決は即刻、打ち首を短期間で執行されていたのである。
ここが刑を執行する場で、火あぶり用の鉄柱などが残っており,
ここだけひんやりとした空気が流れていたのは、気のせいだろうか。平和島に
到着した。途中少し贅沢にスカイラークで昼食を取った。足がぱんぱんになり、
よたよただったが初回のわりには、上出来だろう。帰りの電車の中で一日の
出来事を振り返ろうとした時、疲れと電車のリズムに酔い、睡魔に吸い込まれた

平成8年5月18日(土)快晴 平和島〜鶴見(2回目)
2次宿場 川崎 江戸k後期男1080女1353
平成男115513女101467
江戸から六郷川を渡り武蔵国に入る。(東京から多摩川渡り神奈川に入る)
川崎は東海道が設置されて22年後に五十三番目として、最後に出来た宿場である。
六郷川の橋は江戸中期(1707)流された。この川に橋が架けられたのは
明治7年でそれまでは船渡しで、船賃一人十文(約45円)だった。
これだけ大き川で又木造で橋を建造しても台風で流されてしまう、ならば江戸の
治安も兼ねて橋をかけるのを止めようと幕府は政治的判断をした。
現在は川の流れてない中州で野球やサッカー場になり市民の憩いの場所になっている。
今までは通り過ぎていた、ありふれた風景でも旅の途中で触れると
感動を覚える事を知った。
多摩川を渡った付近に当時、煮染煮豆等の茶店が繁盛していたと言う記述がある。
橋を渡り終えて少し進み路地を覗くと、角に甘納豆屋があったので思わず声をだした。
「豆屋がある!」 驚いた妻が、「どうしたのよ」
「昔からここらに豆屋があったんだよ」と資料を見せる。
店の主人に「創業は古いんですか」と咽元まで出たのですが、聞けないまま店を出た。
話しかける事の難しさ、なぜ一言がでないんだろう。
反省しきりの私です。いろいろの種類があったが大粒を少しだけ量り売りで買い求めた。
甘納豆は甘くて美味くて疲れている体にエネルギーをハートには休息を与えてくれる。
平成5年に全国で初めて交差点にエレベーター付きの横断歩道設けて
ハローブリッジと呼ぶ。
地方から来た人に「べご(牛)も乗せて良いんだべか」と尋ねられそうだ。
六郷橋

近くに競輪場と競馬場があるので、豊かな町なのであろう。
お昼は街道沿いにあるデニーズで殿様気分で少し贅沢にランチをとる。
本来は、塩おにぎりと沢庵で済ませ、水筒で喉の渇きを癒せば当時の旅の模造を
味わえるかもしれないが
私たち夫婦は食べることが大好きなので、今回の旅はダイエットにはなりません。
断言できます!!!!。
途中から旧街道は現在の幹線道路から右にはいる。
しばらく歩くと芭蕉句碑 【麦の穂をたよりにつかむわかれかな】
私も一句 【ぬかる道手を差し伸べる夫です】 どう?どう?いけてるかな?
東海道の道幅は駕篭2挺が通れる二間(3,6m)が主で品川宿の場合で
三間から五間くらいの道幅があり、このような大きな道筋は
[往還通掃除町場]というようにそれぞれの掃除の受け持ちがあった。
江戸から五里目の一里塚あり。
鶴見宿までやっと到着!つかれた。ママの方が元気なのが悔しい。
慶長のころより米饅頭が名産と資料にあるので気に
かけながら歩いていたら京浜鶴見駅近くで
米饅頭屋あり!感激!!店内には当時の挿絵もあり、
間違い無く老舗,伝統が偲ばれる。
今日の旅は甘納豆で始まって饅頭で終り。いつの時代も、
食べる楽しみが一番疲れをとる良薬だって事でしょうか。
ああ美味かった。 京急鶴見駅
鶴見


平成8年6月1日(土)快晴 鶴見駅〜東戸塚 (3回目)
資料片手に、何処まで進めるか、私の住んでいる町に向かうので楽しみである。
早速生麦事件の記念碑有り。『薩摩藩の島津久光一行、馬600駄・長持80棹
数門の砲車も曳いた総勢七百人を超える人数で薩摩
帰る途中1862年8月21日午後2時、灼熱の日に英国人が馬で行列に
紛れ込んだ為《無礼者!!》と左肩から腹まで切り下げた。
この事件がキッカケで、徐々に幕府が弱くなり、薩摩藩を維新の主役へと導いた。
参勤交代の制度が出来て、140年後の事件だ。
生麦5丁目で街道両脇に100メートル以上続いて魚屋が並んでお店がある。
まるで市場のように朝の賑わいが凄そうだ。裏手に鶴見川があり海に続いているので、
漁師町なのだろうか?歴史がありそうだ。一歩路地に入ると長屋の家があって
懐かしいポンプ式の井戸もあった。冷たい水が出るんだよね。
玄関も引き戸で、硝子が周りを白で縁取りされて落ちないようになっている。
懐かしい光景に自分が幼き頃遊んでいる姿がうかぶ。妻も何か感じているようだ。
麒麟ビール工場の前を通り過ぎようとしたが、冷たいビールの誘惑に負けて、工場内の
レストランに入り、地ビール横浜を飲む。ここでだけで味わえる醍醐味だ!たまんね〜。
ここはデート場所の穴場かも、子供たちに教えてあげよう。
生麦事件 麒麟ビール工場


3次宿場 神奈川宿 江戸5793男2944女2849
平成116243男116736女113632
外国人居留地(1858〜1899)横浜らしくオランダ領事館とアメリカ領事館跡がある。
浦島丘町にある蓮法寺に着いた。
この寺は誰でも知っている昔話で有名な浦島太郎齢塚がある。
確かに境内のなかに石碑と亀型の墓石がありました
こんな身近にあったなんて驚きです。
当時この辺りは波打ち際で、切り出た海岸。もっとも現在は高層ビルが彼方まで
続いて海は見えない。
広重が風景に描いた田中屋が料亭旅館として現代も営業を続けている。
その田中屋の近くにある台場公園で、途中で買った特製ほかほか弁当を食べる。
アメリカ使節、ペリー提督が来た江戸後期、100戸前後しかなかった
武蔵国久良岐郡横浜村。現在では340万人に迫る勢いらしい。
浅間町に入ると浅間神社の鳥居があり【旅鏡】に「富士浅間の社あり、
此地に一つの暗窟有。これを富士の人穴といふ」ようするに穴は富士山まで
続いていると言うのであるが戦後の発掘で横穴古墳だったという。
言い伝えには深い訳があるに違いない。
しばらくして横浜で3番目に長い帷子川(17,34km)に着く。
ちなみに1位は鶴見川(28,6km)一番短いのは鴨居川で100mである。
この帷子川の話を西区岡野町にある煙草屋のじいさんに聞いたことがある。
大昔上流で戦が頻繁にあって鎧の肩の部分が流れて来たので、帷子(かたびら)川と
呼ばれるようになったとの事。あのじいさん元気にしているだろうか?
しばらくいくと、縁日だろうか、沢山の屋台が並んでいて老若男女で
ごった返している。焼きトウロモコシを買って歩きながら食べる。
甘味がじわり広がり、水分がのどを潤おす。
豪快にむしゃぶる味は開放感が重なり絶品で旨い。最高!と叫びたい気分だ。
オランダ領事館 浦島太郎塚



